 京跡・宮跡
京跡・宮跡二条院候補地(陽成院跡)
京跡・宮跡京都平安時代
平安時代の陽成上皇が御所とした邸宅跡。また、源氏物語の主人公である光源氏の邸宅のひとつである二条院の候補地ともなっている。
歴史・概略
陽成天皇(ようぜい...
 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡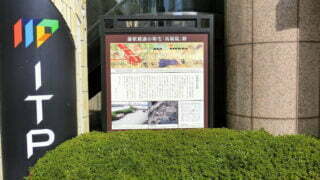 京跡・宮跡
京跡・宮跡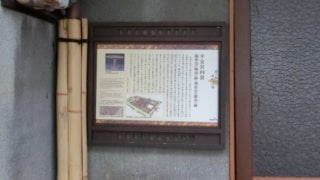 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 寺社
寺社 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡