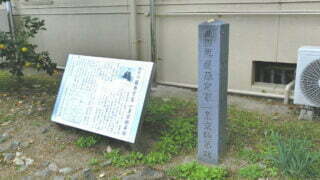 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡藤原定家 一条京極第跡
京都邸宅・住居跡鎌倉時代
平安時代末期から鎌倉時代初期の貴族・藤原定家の邸宅跡。
貴族というより歌人としての名声が高く、特に小倉百人一首の選者として広く知られている。
歴史・概略
...
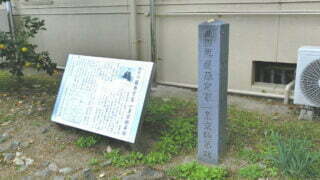 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 墓・慰霊碑
墓・慰霊碑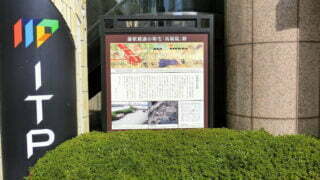 京跡・宮跡
京跡・宮跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 寺社
寺社 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 京跡・宮跡
京跡・宮跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡 邸宅・住居跡
邸宅・住居跡